オーバーラップに関する説明 ― 2006年02月09日 22:09
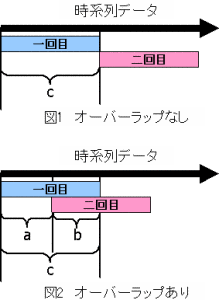
下記の記事については、
http://cessna373.asablo.jp/blog/2007/05/10/1499595
にて訂正を行っております。ご確認ください。
-----------------------------------------------------------------------------
オーバーラップに関して定義が出てきましたので、補足として図で説明してみます。
まず図の説明ですが。
横軸は時間とであり、矢印上に時系列データ(WAV等の音声データ)があると見てください。一回の解析は解析間隔で設定した幅(c)で計算されます。
図1にはオーバーラップしていない場合のFFTが計算される様子を表しています。一回目の解析データと二回目の解析データはまったく重なっていません(ラップしていません)。
図2ではオーバーラップした場合です。一回目の解析データと二回目の解析データが重なっています。重なり分はbです。この場合は ラップ率=b/cX100(%) となります。
この違いにより、時間当たりの解析回数はオーバーラップを設定した場合には大きくなります。
たとえば、解析間隔 1秒の場合、オーバーラップしない場合には10秒間では10/1=10回解析します。同じ条件でオーバーラップ率90%の場合には1+(10-1)/(1-0.9)=91回解析します。
したがってほぼ9倍解析回数が多くなるため、解析の応答性がいい、あるいは短時間で終わる解析にむくということなります。
http://cessna373.asablo.jp/blog/2007/05/10/1499595
にて訂正を行っております。ご確認ください。
-----------------------------------------------------------------------------
オーバーラップに関して定義が出てきましたので、補足として図で説明してみます。
まず図の説明ですが。
横軸は時間とであり、矢印上に時系列データ(WAV等の音声データ)があると見てください。一回の解析は解析間隔で設定した幅(c)で計算されます。
図1にはオーバーラップしていない場合のFFTが計算される様子を表しています。一回目の解析データと二回目の解析データはまったく重なっていません(ラップしていません)。
図2ではオーバーラップした場合です。一回目の解析データと二回目の解析データが重なっています。重なり分はbです。この場合は ラップ率=b/cX100(%) となります。
この違いにより、時間当たりの解析回数はオーバーラップを設定した場合には大きくなります。
たとえば、解析間隔 1秒の場合、オーバーラップしない場合には10秒間では10/1=10回解析します。同じ条件でオーバーラップ率90%の場合には1+(10-1)/(1-0.9)=91回解析します。
したがってほぼ9倍解析回数が多くなるため、解析の応答性がいい、あるいは短時間で終わる解析にむくということなります。
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://cessna373.asablo.jp/blog/2006/02/09/247376/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。